どうもみなさんこんにちは。
高知県で1児のパパとして奮闘中のかっぱパパです。

ねぇねぇ、みんなの子どもはすぐに寝てくれる?
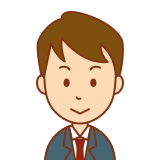
うちは全然寝てくれんなぁ。
寝れる様に早めに寝室に行くんだけどね〜。
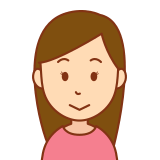
うちも寝てくれない。
結局寝る時間が遅くなって、朝寝坊・・・

やっぱりみんなも寝かしつけに苦労してるよね〜。
よ〜し、今日はそんなみんなにこんな話をするよ〜。
みなさん寝かしつけで苦労してる人は多いのではないでしょうか?
睡眠は体や心の調子を整えたり、記憶や認知機能にも影響すると言われています。
それは、大人も子どもも同じです。
- 子どもが夜寝てくれなくて朝寝坊してしまう
- 子どもが大きくなってきたのに1人で寝てくれない
今日は、こんな悩みを持って人に記事を書いてみました。ぜひ最後まで観覧していってください。
子どもがよく寝る7つのテクニック
- 時間に余裕を持って起きる
- 昼間に日差しを浴びる
- お昼寝、休憩時間を作る
- 夜に向けて、眠くなる時間を作る
- 夜、1人になれる時間を作る
- 規則正しいリズムの生活を気をつける
- 自分の睡眠リズムを見直す
それでは、1つずつ詳しく説明していきます。
時間に余裕を持って起きる
家庭によって生活習慣やリズムが違うため、何時に起きるなんてことは言えませんが、子どもが朝に活動を始めるのに十分に余裕を持って起きるようにしましょう。
もしも、今の時点で夜更かしに慣れてしまい、朝寝坊が多いなんて場合は早く起きる習慣をつけましょう。無理やり時間を早める必要はありません。例えば、10分や15分ずつなど少し早い時間に起きてもらいながら子どもの体を慣らしていってあげてください。
朝といえばやはり光です。カーテンを開けて太陽の光で起こしてあげましょう。曇りや日当たりの悪い場合は電気をつけて朝が来た事を知らせてあげましょう。
また、声や音にも光と同じ効果があります。優しく起こす声や家族の話し声、台所で朝ごはんを準備する音、音で1日を始まりを知らせることもできます。
そうして、子どもが起きてきたら目を合して挨拶をしたり、抱きしめて頭を撫でてあげたりなど親子のコミュニケーションが始まる時間だと教えてあげましょう。
昼間に日差しを浴びる
朝に日差しを浴びると体温が上昇し、頭がすっきりと目覚めてきます。まだ、学校や保育園などに言っていない子どもの場合は、午前中にお散歩や買い物に行くのもおすすめです。学校に通っている子どもなら、歩いて学校に行くことや早めに学校に行ってグランドで遊べたら子どもも楽しいはずです。
昼間に日差しを浴びることはとても睡眠に役に立ちます。日差しを浴びている間はメラトニンの分泌が減り、暗くなってくるとメラトニンが分泌され眠くなってきます。昼間に散歩に行けば親である私達の眠りにも役に立つため、昼間は子供と一緒に屋外へ出て遊ぶように心がけましょう。
お昼寝、休憩時間を作る
まだ小さく、お昼寝をしている子どもにとってお昼寝は、1日が終わって夜寝るための休憩時間です。子どもがお昼寝しない日やお昼寝卒業しているこの場合は、眠らなくていいので少し休憩する時間をとりましょう。
お昼寝は夜までの日課を無事に終えるための休憩時間と考えます。ただし、夜に寝れなくなるくらいのお昼寝は良くありません。お昼寝は体とお脳に休息を与えて1日の行動の効率を高め、学習や記憶に役立ちます。
夜に向けて、眠くなる時間を作る
夜ご飯の後は1日を終える途中にいると考えましょう。
ご飯をお腹いっぱい食べることが眠りを助けてくます。お腹が空いていると眠くなりませんよね?朝までお腹が空かないようにしっかり食べましょう。また、夜ご飯から眠るまでの時間が長くなるとお腹が空いてしまうため1回チェックしてみてもいいかもしれません。
夜ご飯の後は少しづつ照明を減らして夜になったことを教えてあげます。騒々しい音楽やテレビの音も減らし落ち着いた雰囲気を作ることも大切です。
はっきりとした結論が出てるわけではありませんが、ブルーライトが睡眠に悪影響があると言ってる専門家もたくさんいます。寝る前にはテレビやパソコン、スマホにタブレットを使うのは避けて子どもが眠りにつきやすくしてあげましょう。もちろん大人も同じです。
夜、1人になれる時間を作る
寝る前にベッドで本を読んであげたり、子守唄を歌ってあげたりする事で子どもがリラックスして1日の終え、親の愛を感じながら眠れるのは本当にいい事です。でも、子どもが寝るまで背中をなでてあげたり、子どもが目を覚ますたびにパパやママを探したりする習慣は、結果的に子どもの睡眠の質を下げる可能性があります。それは、寝るために人の力を頼っているためです。
まだまだ小さい子どもの場合は仕方ないですが、大きくなってきた子どもには、夜は自分で寝る時間であることを少しづつ教えていきましょう。
最初のうちは、すぐに寝付けず、目を覚ましても大丈夫です。パパやママを探して寝なくちゃと思うより、少しだけ1人でいればまた眠くなると思えれば子どもの心も軽くなるでしょう。これを繰り返して1人で寝ようとすれば、すぐに眠りにつける様になるでしょう。
規則正しいリズムの生活を気をつける
規則正しい生活を行うには、いつが朝なのか、いつが夜なのか、いつ一緒に遊んで、いつ1人で寝るのかを学習していかなければなりません。そうして作った1日の習慣を、できるだけ維持していきましょう。絶対守らなくてはいけないわけではありません。
可能なら平日も休日も同じリズムで過ごしてみましょう。もちろんお出かけをしたり、病気になったりでリズムが崩れることもあると思いますが心配する必要ありません。病気が治るように乱れた習慣もいくらでも直すことができます。
自分の睡眠リズムを見直す
今までは子どもの睡眠について話してきましたが、親の自分達はどうでしょうか?
もちろん子どもと同じように親の睡眠も大切です。子どもの眠りは親の眠りに似てきます。
例えば、親が眠りに対してネガティブな発言をしたり、眠りを邪魔するような行動をしたりすると、子どもは真似をしてしまいます。
子どもが朝元気に起きてくるには一緒に元気に起きれる親が必要で、夜に子どもがスマホなど見ないようにするには親が管理をする必要があるのです。
子どもはまだ睡眠の学習段階。まずは親が眠りを大切にし、よい睡眠環境を作っていきましょう。
まとめ:24時間の体のリズムを管理しよう
今回は、子どもの睡眠について話をさせてもらいました。
ポイントは以下の通りです。
- 時間に余裕を持って起きる:朝に活動を始めるのに余裕を持って起きる
- 昼間に日差しを浴びる:昼間は子供と一緒に屋外へ出て遊ぶ
- お昼寝、休憩時間を作る:お昼寝は夜までの日課を無事に終えるための休憩時間
- 夜に向けて、眠くなる時間を作る:夜ご飯の後は1日を終える途中にいると考える
- 夜、1人になれる時間を作る:夜は自分で寝る時間
- 規則正しいリズムの生活を気をつける:平日も休日も同じリズムで過ごす 絶対ではない
- 自分の睡眠リズムを見直す:子どもの眠りは親の眠りに似る まずは親が睡眠を大切に
上記の内容を意識して、少しづづ睡眠のリズムを作っていきましょう。
睡眠は脳の発達にも大きな影響を与えています。
1日の疲れを回復させるだけではなく、1日のため込んだ情報を整理し、記憶してくれます。
そうして次の日、また元気に遊び、学び、健康に生活ができていくのです。
以上、かっぱパパでした。まったね〜。
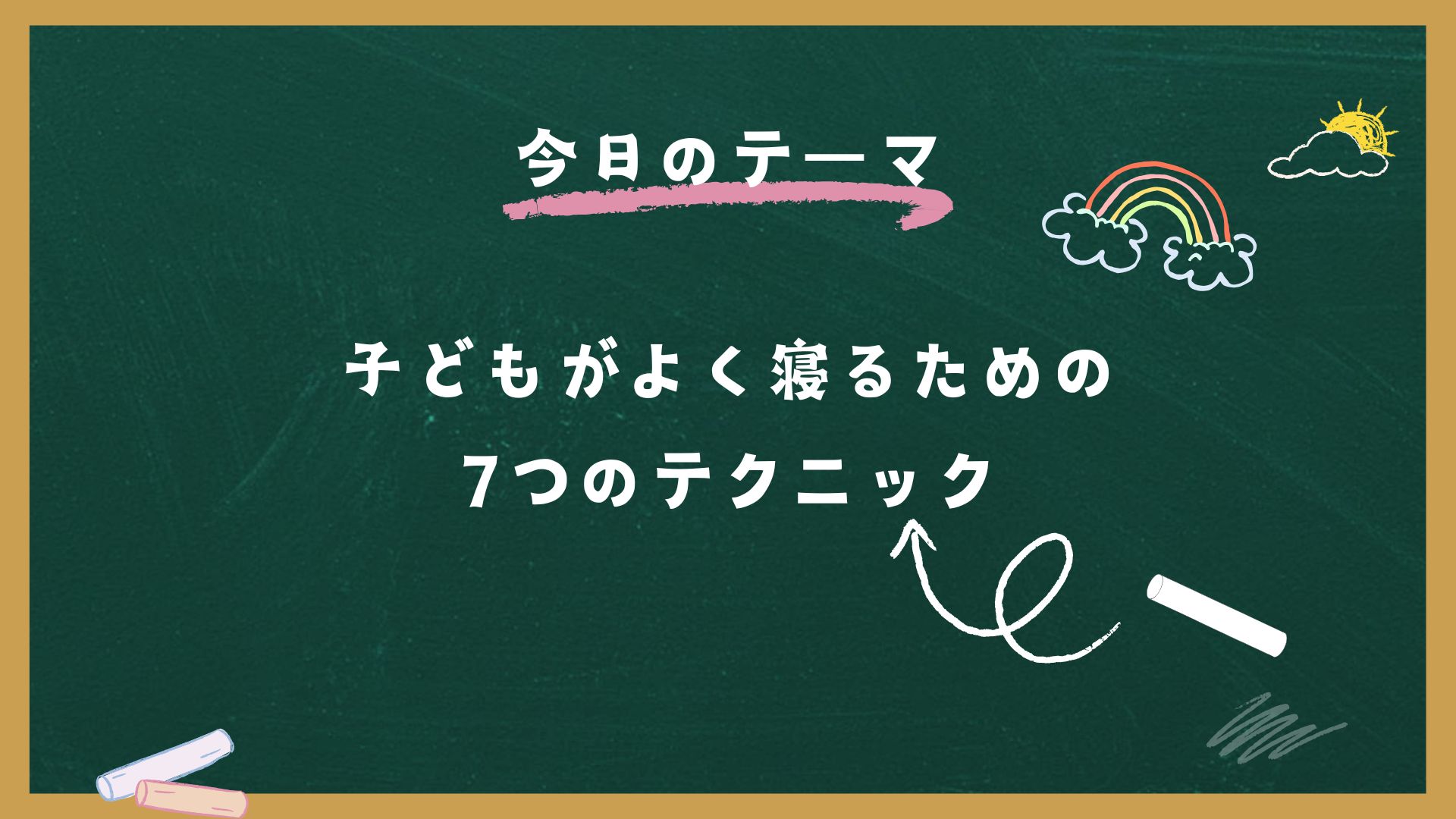

コメント