どうもみなさんこんにちは。
1児のパパとして奮闘中のかっぱパパです。
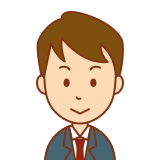
うちの子はテレビつけてたらおとなしくしてくれてるし、お利口だなぁ

子どもがおとなしくしてくれていると大人は楽だけど、本当にそれは子どものためになってるかな?
大人としたら、子どもがおとなしくテレビやYouTubeをみてくれていたら忙しくなくて楽ですよね?
でもそれって大人にはいいけど、子どものためになっているのでしょうか?
子どもの運動不足により体力低下や肥満などは昨今問題となっています。
そこで今回は、子どもにとっての運動の必要性、適切な運動量について解説させていただきます。
- 運動が子どもに与える影響
- 年代別の子どもの適切な運動量
子どもにとって運動の必要性
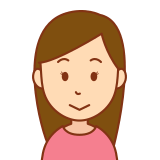
うちの子は全然じっとしていられないんだけど・・・
このままで学校なんか大丈夫かしら?

確かに子どもってなかなかじっとしてくれないよね。
それにはちゃんと理由があるんだよ。
子どもは食事の時間に歩いてみたり、授業中にゴゾゴゾしたりとなかなかじっとしていることができないですよね?
そして親はそれをみて、「このままで入学してから大丈夫?」や「せめて授業の時間は大人しくしていてほしい」こんなことを思う人は多いのではないでしょうか?
では、子どもはどうしてじっとしていることができないのでしょうか?
それは、子どもは動きながら学んでいるからなのです。
じっと寝ているだけに見える赤ちゃんも、手を伸ばしてみたり、足を蹴ってみたりなど色々と体を動かしています。ハイハイが始まると目を離すことができなくなります。
この様に、子どもが絶えず動き回るのは、手で何かを掴む能力や足で立ち上がる能力をレベルアップさせようとしているのです。ゲームでレベルアップして新たな世界が広がると面白いように、子どもは動きをレベルアップ(学ぶ)しようとしているのです。
運動は脳の発達にも影響する!?
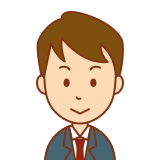
やったぁ。やっと明日は仕事が休みだぁ。1日家でのんびりしよ〜。

まぁ確かに仕事で疲れてゆっくりしたいのはわかるけど、運動することが子どもの脳の発達に影響があるって言われてるんだよね。
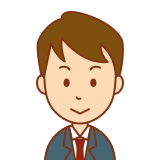
えっ!!そうなの!?
どんな影響があるっていうの?
多くの親が、運動は子どもに対して大切であることは知っていると思います。
たくさん動けば体も強くなるし、睡眠にもいい影響があります。何より子どもが楽しく過ごすことがでますよね。
でも、運動や体を使った遊びよりも教育や勉強が大切になったのでしょう。小さい頃から習い事をし、年齢が上がることで勉強にかける時間が増えています。その結果、現代の子どもは1998年の子どもたちより体が弱くなっているそうです。
アメリカのカール・コットマン教授は、認知症と脳の老化に関する研究の結果、老年期まで脳の健康を維持していた人々は運動をしていることを発見したそうです。
アメリカのテキサス大学サウスウエスタンメディカルセンターの研究では、有酸素運動を1年間続けた高齢者のグループは、記憶力検査の点数が上がったと報告しています。運動で心肺機能が向上し、血液によって酸素が円滑に供給され、脳機能が向上したのでしょう。
つまり、体を動かすことは、学習や記憶になくてはならないものなのです。
年代別の必要な運動量
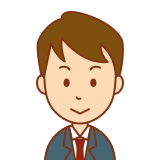
運動が体にも脳にもいいことはわかったけどじゃあ一体どれくらいの運動すればいいの?

それはWHOが発表しているガイドラインがあるからそれを参考にしてみよう
WHO身体活動・座位行動 ガイドライン
1歳未満 ・1日に数回に分けて身体活動をします。特に床で他の人と関わり合いながら遊ぶ時間を持ちます。多ければ多いほどいいでしょう。
・1時間以上ハイチェアやベビーカーに固定するのは避けましょう。1〜2歳 ・1日に180分以上身体活動をします。
・適度な強度から激しい強度までの多様な身体活動をします。多ければ多いほどいいでしょう。
・1時間以上ハイチェアやベビーカーに固定したり、長く座らせるのは避けましょう。
・テレビを見たりビデオゲームをしたりなど、静的な活動は2歳以降、1時間未満にします。短ければ短いほどいいでしょう。3〜4歳 ・1日に180分以上、多様な身体活動をします。
・60分以上の適当な強度から激しい強度までの多様な身体活動をします。多ければ多いほどいいでしょう。
・1時間以上ハイチェアやベビーカーに固定したり、長く座らせるのは避けましょう。
・テレビを見たりテレビゲームをしたりなど、静的な活動は1時間未満にします。短ければ短いほどいいでしょう。5〜
17歳・1日平均60分以上の適度な強度から激しい強度までの多様な身体活動をします。
・1週間続けて有酸素運動をします。
・激しい強度の有酸素運動と筋肉や骨を強化する運動を週3回以上します。
・静的な活動時間を制限し、特に余暇のデジタルメディア鑑賞時間を適切に制限します。
この内容を自分の子どもに当てはめてみてください。まず、5歳未満の子どもなら動き回っていることが基本だと思ってもいいでしょう。
WHOのガイドラインで提示しているように、未就学児童は1日にどれだけ運動したかではなく、どうすれば座っている時間を減らし、たくさん動けるかを考えるべきなのです。
基準に合わせてスポーツなどの習い事をする必要はありません。公園に行って運動するなど、限定された場所や姿勢を子どもに強要しないようにすれば、自然と解消する問題です。
まとめ:座る時間を減らして、賢い脳をつくろう
今回は、子どもの運動量や運動の意味について解説させていただきました。
今回のポイントは以下の通りです。
- 子どもは運動をすることでレベルアップし、学んでいる
- 運動は認知機能や記憶力の発達に影響している
- 運動は座る時間を減らすように工夫する
上記のポイントに気をつけながら子どもと楽しい時間を過ごしてみてください。
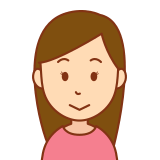
子どもは動きながら色々と学んでいるってことなんですね。

そうそう。子どもが自然の中で制限なく自由に動き回ることで集中力がついたり、いい子になるって言っている人もいるんだよ。
日々の仕事で疲れていると思いますが、時にはキャンプや登山、釣りなど自然の中で子どもと大いに動き回ってみてはいかがでしょうか?
以上かっぱパパでした。まったね〜。
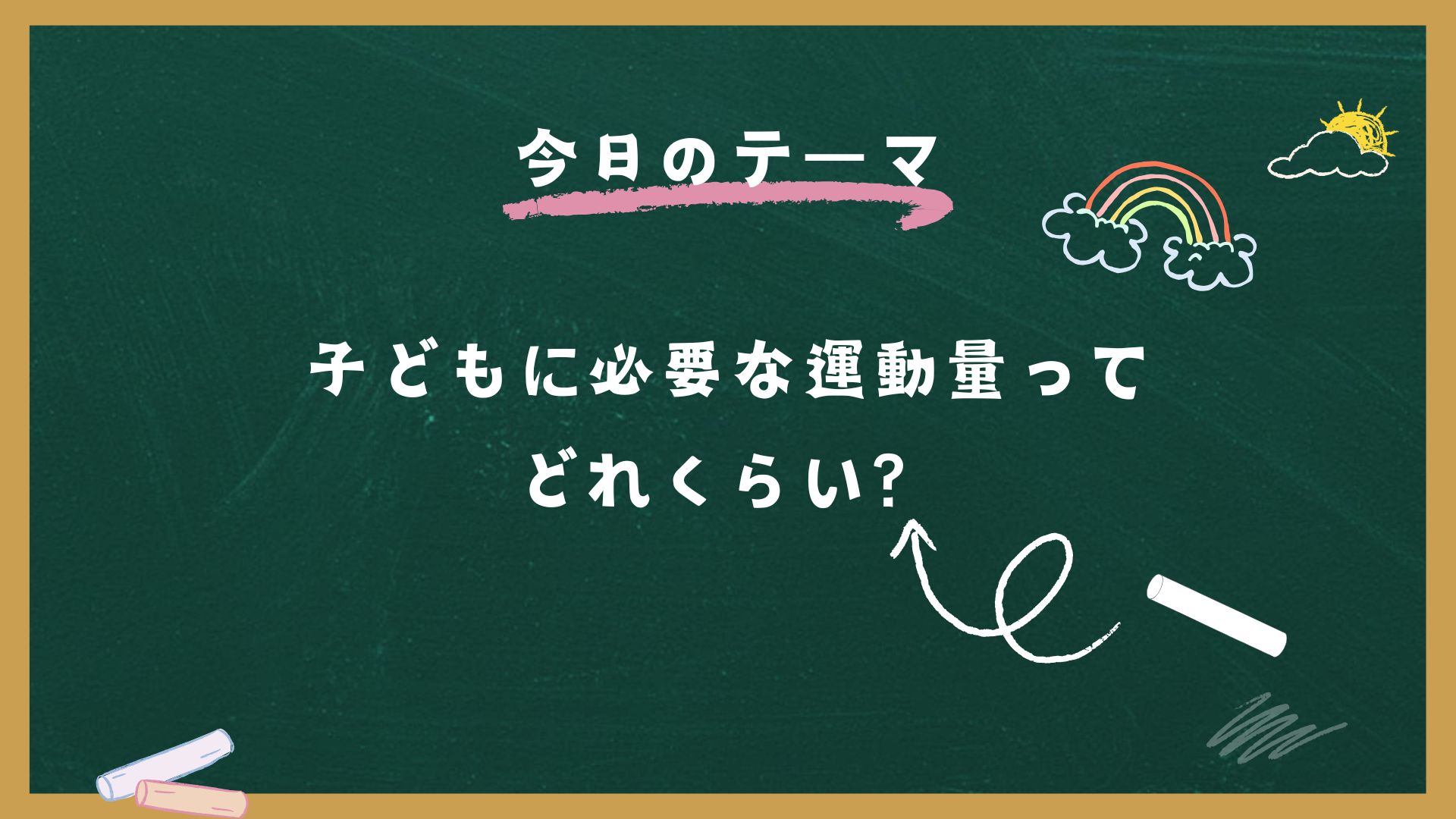

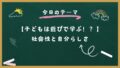
コメント