※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
どうもみなさんこんにちは。
1児のパパとして奮闘中のかっぱパパです。

みんなは「読み聞かせ」してる?
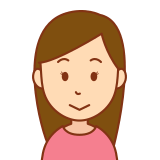
「読み聞かせ」って大事とは聞くけど何がそんなに大事なのかな?
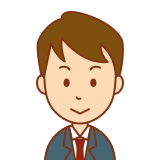
えっ何それ?本読みのこと?

じゃあ今日はそんなみんなに「読み聞かせ」について解説していくよ
子育てをしている人なら「読み聞かせ」は聞いたことがあると思います。「読み聞かせ」は子どもの成長に大事と聞いてやってはみていてもどんな意味があるのか、やり方は合っているのかなど様々な疑問があると思います。
そこで今回は「読み聞かせ」について解説をしていきます。今まで、「読み聞かせ」という言葉を聞いた事がなかったという人も最後までお付き合いいただければ幸いです。
- そもそも「読み聞かせ」とは何のこと?
- 「読み聞かせ」のすごい効果
- 「読み聞かせ」の方法
- 年齢別の絵本の選び方、おすすめ絵本
読み聞かせって何?
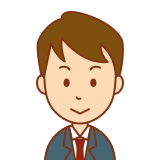
恥ずかしいんだけど、そもそも読み聞かせってなに?

別に恥ずかしがる事ないよ。
じゃあ読み聞かせってなんのことかから説明するね。
「読み聞かせ」とは、親や保育士、教師など大人が子どもに対して、絵本や物語を読み、聞かせることです。
読み手は、子どもたちが興味を持ちそうな本や物語を選び朗読し、子どもたちはその物語聞くことで楽しみ、学ぶ事ができます。
「読み聞かせ」を行うことで子どもは、言葉を覚え、読解力が身につきます。創造性を育み、感情を理解し、共感力を得たりと様々な効果があると考えられています。
「読み聞かせ」は、物語の世界に触れることで学びの基礎となる部分を作ってくれているのです。
定期的な読み聞かせによって、子どもは本に対しる興味や関心を高めます。例えば、寝る前の読み聞かせなどは、寝る前の心を落ち着かせる事ができ睡眠への導入にも役立ち、習慣化しやすくなります。

私は寝る前の読み聞かせは、習慣化してるよ。
読み聞かせは何歳から始める?
「読み聞かせ」にいつからという明確な答えはありません。早い人では胎児の時から読み聞かせするという人もいます。
諸説ありますが出来るだけ早く始めることで、子どもの言語発達や読解力に効果があると言われています。生後5ヶ月ごろから始めてみるのをおすすめします。
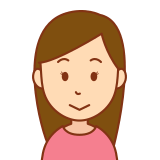
そんなに早くからしたほうがいいんだ

まぁこれはあくまで目安としてだよ
嫌がるようなら無理はしないようにしよう
この頃の子どもは、当然ですが言葉の理解は難しいです。しかし、音やリズムなどにはしっかりと反応を示します。
親の声や表情などから温もりを感じ、安心し、リラックスできます。まずは、スキンシップやコミュニケーションとして始めてみるのもいいかもしれません。
この親と過ごせる幸せな時間が、子どもを自然と絵本好きにするかもしれません。親子で楽しく行える読み聞かせはおすすめです。
読み聞かせはいつまで?
では一体いつまで「読み聞かせ」を行うべきなのでしょうか?それは、10歳頃まで続けましょう。
10歳頃といえば既に小学生になり、1人で読み書き出来る年齢です。また、子どもの言語機能が揃うのは8歳頃と言われています。
何故10歳まで続けるの?
幼児期の「読み聞かせ」は、言語発達が未熟な状態のため、お話から基本的な語彙力や想像力、登場人物からの共感力などが得られます。また、親子のコミュニケーションの時間となるでしょう。
小学生以上になれば、絵本には書かれていない行間が読めるようになったり、表現力や読解力が身につきます。
また、小学生の頃に1日1時間以上本を読んでいた子は、読まない子に比べ、将来本を読む量が2〜3倍になると言われています。
「読み聞かせ」を続け習慣化していきましょう。
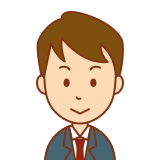
結構大きくなってからも続けたほうがいいんだね

年齢によって効果が違ってくるみたいだね
大きくなると親子のコミュニケーションも減るからいい機会になると思うよ
「読み聞かせ」の効果は?
では、「読み聞かせ」にはどういった効果があるのでしょうか?
言語発達
「読み聞かせ」は、子どもの言葉の理解を広げます。一番重要なのは、どれだけ多くの言葉を聞くかです。また、言葉の量も重要ですが、質も重要です。言葉の質とは、どれだけ多様な言葉を聞くか、それが子どもに適切な言葉か、直接子どもに話しかけているかです。
これにより、語彙力や文法の理解が深まり、コミュニケーション能力が向上します。
また、父親が「読み聞かせ」をする方が言語発達がより促進されると言われています。その背景には、母親は、子どもの理解しやすい言葉を使い、父親は難しい言葉を使う傾向にあるという事です。また、父親は質問がはっきりしていて、因果関係についての説明をよくするという結果があります。

父親じゃないとダメというわけではないよ
意識して難しい言葉を使ってみることで同じような効果は得られるよ
読解力が身に付く
「読み聞かせ」によってお話の内容を理解する力が鍛えられます。物語の展開や登場人物の感情を読み取ることで、より深く文章の意味を理解することができます。
読解力は勉強やテストなどでも重要な能力となってきます。
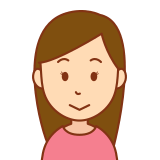
試験問題の勘違いってよくあるもんね
感受性や共感力
物語の世界に入り込むことで、登場人物の気持ちを理解し、寄り添うことが出来るようになります。これは、人の気持ちを理解し、人と関わるうえで大切な事です。
また、保育園などでの読み聞かせは、友達たちと一緒に楽しむことで共感力や他者との関わり方を学ぶ事ができます。
想像力、創造性を育てる
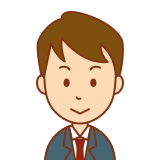
今の時代、クリエイティブな人になってほしいなぁ
「読み聞かせ」は、子どもの想像力を刺激します。子どもは絵本を見ながら色々なことを考えてます。自分ならこうするのにやこんなふうになったら面白いのになどその子ならではのアイデアを生み出します。このような創造的思考が発達することで、問題解決能力や創造性が成長して行きます。
絆を深める
「読み聞かせ」は親子の大切なコミュニケーションの時間です。信頼関係が築かれ、子どもは愛情を感じ、安心感を得ることができます。

親子にとってコミュニケーションは何よりも大事だよ
「読み聞かせ」のコツや注意点
読み聞かせがとても大切であることは理解できたかと思います。
ここでは、読み聞かせのコツを紹介します。
環境を整える
「読み聞かせ」をする上でまず大事なことは、静かで、集中できる環境かどうかです。
テレビが付いていたり、大きな音楽が流れていては子どもは集中できません。集中できる環境を用意しましょう。

せっかくいいことをしていても集中できていないと効果は薄くなるよ
年齢や興味にあった絵本を用意する
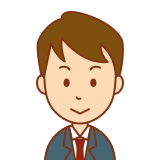
でも、どんな絵本がいいのかなんてわからないよ

まぁまぁ慌てないで
あとでしっかり説明するから
子どもの年齢や興味がある絵本を選ぶことも重要です。子どもが理解しやすく、興味を持てる本選びを意識しましょう。子どもと一緒に図書館などで選ぶのもいいでしょう。
後ほど年齢別のおすすめ絵本で目安を紹介します。
表情や声の使い方に注意する
子どもは、読み手の表情や声に敏感です。表情豊かに読んだり、物語のストーリーに合わせて声や感情を変えることで子どもはより集中できるようになります。
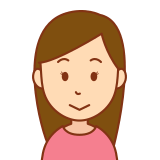
子どもは親のことよくみてるのね
会話や質問の機会を作る
「読み聞かせ」中に子どもに質問などをしてみましょう。「次はどんなことが起こるかな?」など子どもに予測を立てさせ、より子どもの注意を引きつけます。
しかし、注意点もあります。あまり質問や対話が多すぎるとせっかく集中できている子どもの気が削がれる事があります。子どもの集中具合を見ながら適宜質問してみましょう。

せっかく子どもが集中していても親が邪魔してしまう事がよくあるから注意してね
時間を決めて定期的に行う
「読み聞かせ」は継続していくことが重要です。
寝る前など、時間を決めていると子どもを寝る前は絵本の時間、絵本を読んだら寝る時間になるなど絵本を読む準備ができ、寝るための準備にもなり、生活のリズムを作る手助けにもなるでしょう。
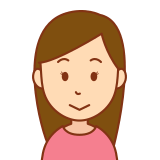
確かに寝る前に「読み聞かせ」したらリズムがついていいかも
親も一緒に楽しむ
「読み聞かせ」はとても効果が高い重要なものです。しかし、重要だからこそ教育だと思い、強要したり、プレッシャーを与えないようにしましょう。あくまで親子のコミュニケーションの範囲でお互いが絵本を楽しみましょう。

昔自分が読んでた本を読んでみるのも楽しめるよ
最近の本も親が十分楽しめるものが多くなってるよ
同じ本を読んでも大丈夫
子どもは好きになった本は毎日のように読みたがります。大人としては、同じストーリーで飽きてしまったり、同じ絵本を読んでもいい効果はないのではないだろうか?と考えてしましますよね?
心配はいりません。好きな本を読んでもらうのは子どもにとって満足度も高いものとなり幸せな気持ちになります。
また、同じ本を繰り返し読むことでより深く意味を理解したり、語彙力が養われます。
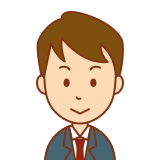
好きな本ならずっと読んでいられるよね
年齢別の絵本の選び方
0歳児
言葉を覚える前のこの時期は、シンプルな絵本を選びましょう。短い言葉の繰り返しや触感などが楽しめるものもいいでしょう。
絵は、色や輪郭がはっきりしており、大きくわかりやすい絵が適しています。
内容としては、日常の生活や身近なものに関連していたり、リズミカルに読めるものをおすすめします。
1~3歳児
言葉を覚えたり、自我が目覚め、成長著しいこの時期には、楽しいと思える絵本を繰り返し読みましょう。
0歳児の時と同じように、シンプルかつわかりやすい絵で少し物語やテーマがある本を選びましょう。
子どもがめくりやすい厚めのページや触感の楽しめるものがいいでしょう。
4~6歳児
この頃からは読み聞かせを落ち着いて聞けるようになるため、少し長めの物語を選んでみてもいいでしょう。冒険もので想像力を育てたり、絵本を通して色々な経験をする事ができます。
7歳児以上
長編の絵本や文学作品を絵本化したものなどを選んでみましょう。複雑なストーリーや登場人物の心情などを読み取ることが出来るものや歴史や文化、科学などの知識を学べるものもいいでしょう。
おすすめ絵本
0歳児
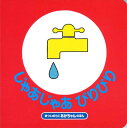 | じゃあじゃあびりびり 改訂 (まついのりこのあかちゃんのほん) [ まつい のりこ ] 価格:660円 |
”じゃあじゃあびりびり”
日常生活の中のたくさんの”音”が詰まっている本です。シンプルかつわかりやすい絵で子どもの興味を引きます。
1~3歳児
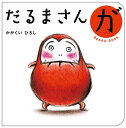 | 価格:880円 |
”だるまさん”シリーズ
子どもから読んでいる大人まで笑ってしまう1冊です。
真っ赤なだるまさんがリズム良く動いたり、音を出したり、何かになったり、子どもを絵本好きにするには最適な1冊です。
4~6歳児
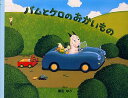 | バムとケロのおかいもの (バムとケロのなかまたち) [ 島田 ゆか ] 価格:1650円 |
”バムとケロ”シリーズ
しっかり者のバムとお調子者のケロがおりなす様々な出来事は、子どもだけではなく大人も引き込まれること間違いなし。
細かい描写やユニークな発想は子どもの想像力を高めてくれるのではないでしょうか?
7歳児以上
 | ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ (おはなしみーつけた!シリーズ) [ 相馬公平 ] 価格:1320円 |
”ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ”
テンポのいい会話を軸に構成された、父子の絆を描いた作品です。自分の父親の涙を見たことがある子どもは少ないのではないでしょうか?
つい涙が出てしまう自分と父親を比較して素朴な疑問を思い浮かび、その疑問に真摯に向き合ったお父さん。心温まるストーリーとなっています。
まとめ:効果が大きいからこそ親子で楽しみながら読み聞かせを
今回は、「読み聞かせ」について解説させていただきました。ポイントは以下の通りです。
- 「読み聞かせ」には様々な子どもの成長を促すいい効果がある
- 効果が高い「読み聞かせ」だからこそ親子で楽しみながら継続することが大事
- 子どもの年齢や興味に合わせた絵本選び
- 決して強要はしない
上記に気をつけながら、親子で「読み聞かせ」を楽しみながら意識的に取り入れてみてはいかがでしょうか?

「読み聞かせ」は子どもにとって重要な効果が得られ、幸福感も高い最高のプレゼントだよ。
以上、かっぱパパでした。まったね〜。
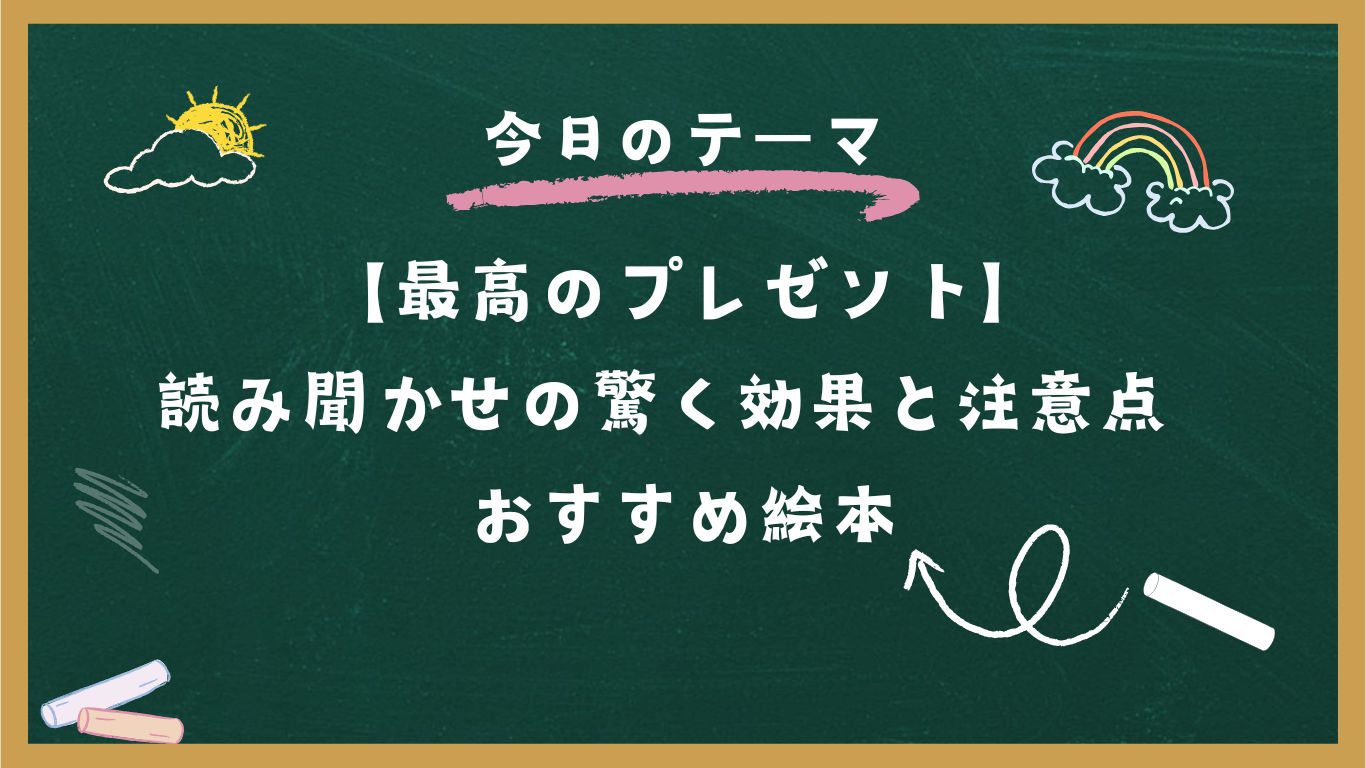
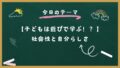
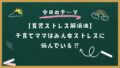
コメント