どうもみなさんこんにちは。
1児のパパとして奮闘中のかっぱパパです。

みんなの子どもたちは何して遊んでることが多い?
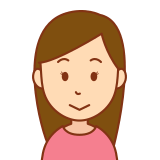
うちの子はまだ小さいからお散歩行ったりしてますね。
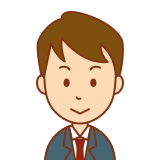
うちは元気に公園で遊びまわってるよ。時々よその子とケンカにならないかドキドキしてるよ。

みんなしっかり遊んでるみたいだね。
元気よく遊んでいる子どもをみていると親である私たちも嬉しい気持ちになりますよね?
そんな子どもたちの遊んでいる様子を見ている中でこんな事を思いませんか?
- ずっと1人で遊んでいるけど友達が出来るのか心配。
- 他の子どもとケンカになりそう。
そこで今日は、子どもが遊びの中で身につける能力について解説していきたいと思います。
- 保育園や小学校で友達ができるか心配。
- 他の子どもとトラブルを起こしそう。
- 子どもに社会性を身につけてほしい。
上記のようなことが気になる方はぜひ最後までお付き合いください。
遊びの中で身に付く社会性
人間は群れを作って生きています。群れを作るというこうとは社会的であるということです。そして、人間は生きるために集まるだけではなく、さらにいい人生を送るために様々のコミュニティを作ります。
人間が社会的に生きていくために必要なことは社会的であるということです。
子どもが1人遊びから複数人の友達と一緒に遊ぶようになると、友達に合わせることが必要となってきます。つまり、社会性は遊びの中で作られていくのです。
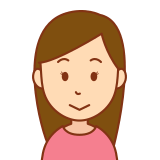
へ〜子どもって遊びながらこんなことを学んでいるんだ。

社会性以外にも遊びの中で学ぶことはたくさんあるんだよ。
友達と遊ぶ時間を大切に!!
一緒に遊ぶということはどれくらい大切なことなのでしょうか?
遊びの中でも、他者と遊ぶことをソーシャルプレイと言います。
子どもの頃に友達とたくさん遊ぶ機会を持って育つと感情反応や認知的処理を上手にこなすことが出来るようになります。しかし、この機能が未熟であればソーシャルプレイの時間が短くなります。
ソーシャルプレイの時間が短くなればなるほど社会性は低くなり、そういった相手とは周りの人も関わりを持とうとしなくなっていきます。
つまり、友達と遊ぶ時間が短い子どもは、社会性が培われなくなるということです。
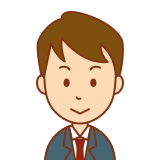
懐かしいなぁ。
昔よく友達と遊んでたよ。

そんな人は大人になった時にコミュニケーション能力は高くなってるかもしれないね。
自己制御を学ぶのも遊びの中
子どもが我慢をすることが増えてくるのは、他の子どもと遊ぶことが増えてくる時期です。
公園の遊具でも順番待ちがあります。かくれんぼなどでも鬼の番が回ってきます。友達がズルをしても叩いたりしてはいけせん。
そこで必要になってくるのが自己制御です。
自己制御とは、自分の行動や感情、思考などを、自分にとって望ましい状態に調整する能力です。
してもいい行動、してはいけない行動は友達と遊ぶ中で学ぶいい機会となります。
間違った行動を続けていると友達との遊びに混ぜてもらえなくなるからです。

このことは大人になっても大切。
最低限のルールを守れないと社会では受け入れてもらえないよね。
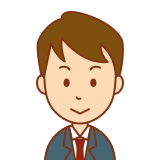
ルールの守るなんてことは当たり前にできる事だと思っていたけど、遊びの中で覚えていってたのか。
遊びの4つの心得
0〜5歳賢い脳のつくりかた スタンフォード大学博士でシリコンバレーで2児を育てたママの脳科学育児コンサルティング 遊びの4つの心得より引用
- 遊びの時間は奪わない
- 自分で決めて行動させてあげる
- おもちゃでは学べないことがある
- ストレスに耐える力を育てる
1.遊びの時間は奪わない
遊びの重要性は前述した通りです。遊びが大切であることを書いた本などもたくさんあります。しかし、遊ぶ時間をスケジュールに組み込む親は少ないのではないのでしょうか?
人間は元々、遊びながら学ぶ力を持っています。しかし、その力も使わなければ発揮することはできません。
言葉を上手く話すためにはたくさん話をすることです。上手に遊ぶためにはたくさん遊ぶことが必要です。
ぜひ子どもが遊ぶことのできる機会(時間)をたくさん作ってあげてください。
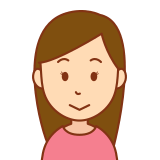
習い事よりも遊びの方が優先ってこと?

別に習い事が悪いって訳ではないよ。子どもが楽しくできているならそれはいい事だよね。
遊ぶ時間もしっかり生活の中に取り入れてあげることが大事って話。
2.自分で決めて行動させてあげる
遊ぶ時間の確保ができれば次は何をして遊ぶかになります。
自分で行動を選択することはとても重要なことです。そのために、必要なことは次の2つです。
- 自分の要求が何なのかを子ども自身がわかること
- 今その欲求を満たすための道具が何かを知っていること
これは、子ども自身が自分のことを理解することや今の環境を理解することに繋がります。
自分で何かを選択するということは、自分自身を理解するということになるのです。
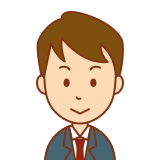
なんでも親が決めていたら、子どもは自分の事がわからなくなるんだね。

最近は、若者の夢離れなんかも言われているね。本当に自分がやりたいことがわからないのかもしれないね。
おもちゃでは学べないことがある
子どもは、大人が思っているように遊びません。自分で、遊び道具を作り遊ぶことができます。初めは買ったおもちゃでは遊んでいても、いつの間にかおもちゃの入っていた段ボールや緩衝材などで遊んでいたりしませんか?
子どもが遊ぶ環境を整えてあげることは親にとってとても重要な役割です。しかし、それは決しておもちゃを与えるという意味ではありません。
今のようなおもちゃがなかった昔の時代は、石を積み上げてみたり、どんぐりゴマを作ってみたりなど子どもが自ら遊びを作り出していました。
そういった能力を子どもが発揮する時に子どもは成長していくのです。
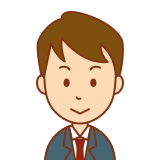
欲しがったおもちゃもすぐに使わなくなったりするんだよね〜。

私の子どもも、おもちゃを片付ける箱の蓋を盾にして遊んでいるよ。
ストレスに耐える力を育てる
遊びは心の健康とストレスに耐える力に影響し、気分を高め、不安やストレスを克服する効果があります。
大人の私たちも休日に趣味や好きなことをすると仕事の疲れを忘れ、また仕事を頑張ろうと思うことができますよね?
それは子どもにとっての遊びであるということです。遊びは子どもの心を守ってくれているのです。

子どももうつ病になったりするんだ。抑圧された生活だと心が不健康になってしまうよ。
小さいうちからストレスの解消の仕方を学ぼう。
おすすめの遊び
- 散歩
- お絵描き
- 公園
- ルールのある遊び
散歩
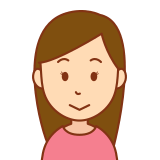
あっ私子ども連れてよく散歩行くよ。

散歩は小さいうちから自然を感じ、いい刺激になるよ。
子どもが小さい時期はなんといっても散歩です。
子どもにとって太陽の光や風、土の感触でもなんでも新たに刺激となり、学びとなります。
子どもが興味を示すのであればただ水の流れを眺めるだけでも十分です。水と一緒に流れてくる葉っぱなどをみて子どもながらに水と葉っぱの関係を考えます。
また、陽の光を浴びることは睡眠を促してくれますし、歩けるようになった子どもにとってはとてもいい運動にあり、ご飯もよく食べるようになるでしょう。
お絵描き
子どもは自分が行った行動によって起こる変化を楽しんでいます。
お絵描きなどはその1つの例です。
汚れの落ちやすいペンなどを使って思う存分に書いてもらいましょう。外で砂に木の枝などで書くなどでも構いません。
小さいうちは絵になる必要はありません。色などもなんでもいいでしょう。
子どもが色や自分の動きに集中できるようにしましょう。
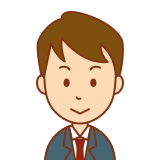
ただボールが落ちるので笑ったり、せっかく積み上げた積み木を倒して遊ぶのも変化を楽しんでるってこと?

それも自分が与える影響で変化が起こることを楽しみ、学んでいるんだろうね。
公園
公園は子どもにとっての社会です。
公園にはたくさんの子どもたちがいます。年齢や性別の違う子ども、1人で遊んでいる子や友達同士で遊んでいる子どもたち。
自分の子どもはどういう行動に出るでしょうか?一緒に遊びたくても自分からいけない子や友達の中に入れず傷つく子もいるかもしれません。もしかすると遊びたくてちょっかいを出してケンカになることもあるでしょう。
だからといって公園に行ってはいけない訳ではありません。子どもにも経験が必要なのです。
子どもたちはそうやって一緒に遊ぶ方法を学ぶのです。

少しでも他の子に迷惑になるような事があれば止めたくなるよね。
でも、なんでかんでも親が先に止めていたら子どもが学ぶチャンスを奪っているかも。一歩引いて見守るのも親だよ。
ルールのある遊び
公園に行って子どもの社会に入っていくようになりました。他の子どもと遊ぶ中で必要なことがルールを守ることです。
ルールを守れなければせっかく入れた社会から追い出されてしまうかもしれません。そこでおすすめなのがルールのある遊びです。
じゃんけんであったり、しりとり、3〜5歳頃になれば簡単なボードゲームもできるようになります。
初めはルールを守れなかったり、ゲームに負けて怒ったりすることもあるでしょう。それでも大丈夫です。大人は一緒に遊ぶことに慣れていない子に配慮をし、少しずつ学べばいいのです。

私の子どもは小さい時からしりとりなんかが好きだったよ。
そのおかげか比較的ルールを守ることはできている気がするよ。
まとめ:遊びは自我の発見と社会性の始まり
今回は、子どもの遊びについて解説させていただきました。
ポイントは以下の通りです。
- 遊びは自己制御や社会性を学べる
- 遊びの時間を奪わず、行動は自分で決める
- おもちゃだけが遊びではない
上記に気をつけながら子どもが自分を理解し、社会に適応できるように親は温かく見守ってあげましょう。
勉強や習い事もいいけれど遊ぶ時間もしっかり作ってあげましょう。

私の考えとしては、何事もバランスが大事。習い事も遊びもどっちも大切だよ。
そのバランスは、子どもによって違いがあるからそれを親がわかってあげることが大事なんじゃないかな?
以上、かっぱパパでした。まったね〜。
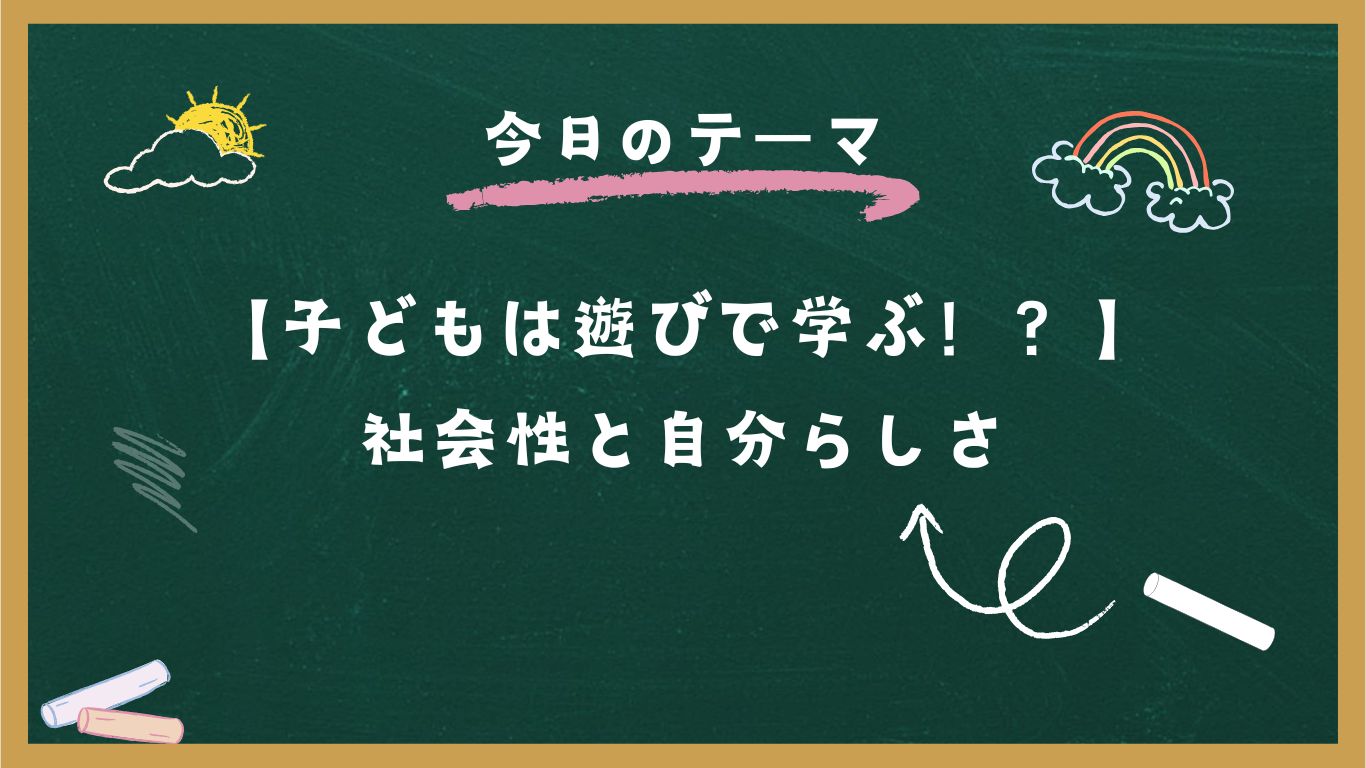

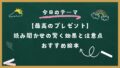
コメント